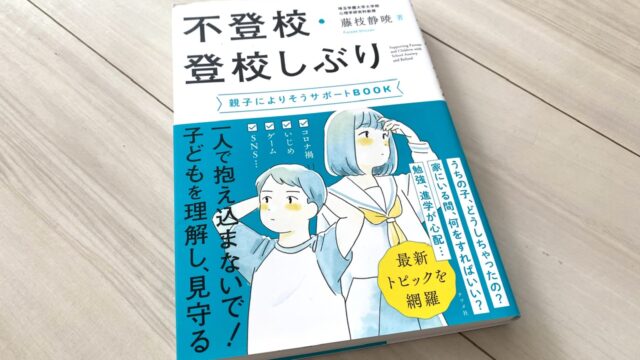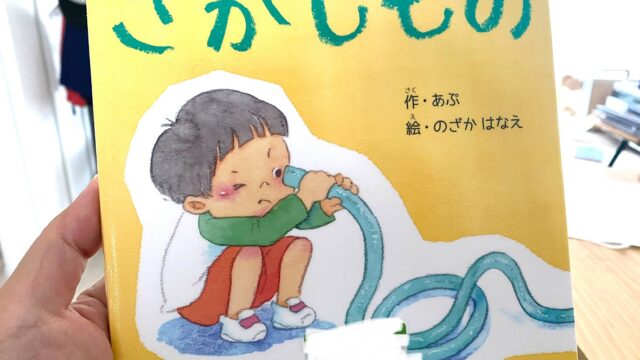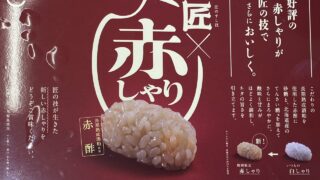【私も理論家になりたい!】看護理論家になるための6ステップを解説!

- 看護師として長くやってきたけど、看護理論家にはなれないの?
- どうやったら看護理論家になれるの?
そんな疑問にお答えします。
海外にはナイチンゲールやヘンダーソンなどの著名な看護理論家がいますよね。
日本にも日本独自の文化を背景として考えられた理論があり、それを提唱した看護理論家がいます。
その例を見ながら、次に理論家になるための流れをステップ形式でお伝えしていきます。
私は看護師として15年働いたのち、退職。今は子育てのかたわらライターとして生活しています。
目次