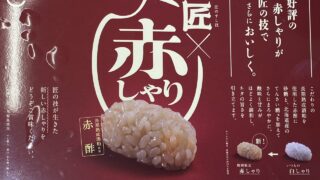〖マーケティング戦略〗キンコン西野さんとBリーグ島田チェアマンの会議が有益すぎたのでまとめてみた

先日、YouTubeのキングコングの西野さんのチャンネルで『ニシノコンサル』という企画を拝聴しました。
内容は
- Bリーグチェアマンの島田慎二さんと
- B1・B2チームの取締役の方々が、
- キンコン西野さんに悩みを相談してアドバイスをもらう
という形式の対談でした。
それがものすごく勉強になったので、今回は自分のように無知でも後から見返してわかりやすいように簡潔にまとめてみました。
今回のポイントはマーケティングにおいて重要な、
- 集客
- 作る
- 届ける
この3つです。
西野さん自身も中学時代にバスケットボールをしていた経歴があるとのことでした(内容には関係ないけど勝手に親近感w)。
目次
前提:Bリーグの概要を知っておく
- Bリーグ自体は8年前から誕生
- 経営状況は、一旦コロナで低迷しつつもトータルで見ると右肩上がり
- 今はB1-B2-B3というチーム分類。
- 2026年からは新たにBプレミアムとBワンに分類となる。
- Bプレミアムは収益が12億円以上、平均集客4000人以上、アリーナ基準を満たすという条件。
- Bワンは収益が4億円以上、平均集客2400人以上という条件。
- 1チーム年間60試合。内ホームゲームは30試合。
今回の目的は、Bリーグの経営力を向上させたいということ。
- 集客
- ファンの獲得
- エンタメ
- 長期目線
について悩みに答える形の勉強会という感じ。
参加者は西野さんと島田チェアマンに加え、
- 佐賀 B1
- 福島 B2
- 秋田 B1
の3チームの取締役の方々が悩みを持ち込んで相談するスタイルでした。
悩み:地元のクリエイターを育てるには?
悩み相談
- 今年からクリエイターを変更した。
- 以前からの方と新しい方の意見がバチバチしている。
- どういったコミュニケーションを取れば良いか?
→クリエイターがお互い「これやりたい」となるのは当然。
圧倒的なTOPが必要。(動画では天皇と表現されていました)
この役目は経営者ではない。ディレクターじゃなきゃいけない。
<コミュニケーションの具体例>
普通にそのまま自分の案を持って行っても通らない。
引き出したアドバイスの中で選択するワザ。
まずは相談ベースで聞きに行く。
「教えてください」
「これいいっすね」「もっとください」
「それもいいっすね」「もっとください」
自分の案と同じことを引き出されたら
「それいいっすね」「それください」
リーダーには懐柔力が必要。
さらに加えて、経営もできるとなお良い。
しかし、こういった人材を育てようとすると難しい。
演出力×経営力は育成が難しいのだ。
現実問題、お金を作れる人と、どれだけ教えてもお金を作れない人はいる。
教育の限界はあるので「教育できないことはある」という知るべし。
教育で伸びないところに投資し続けてもムダになる。
解決策は、よそから引き抜く、呼ぶこと。(買うという表現をされていました)
収益源が限られると、作れるものも限られてくる。
負のスパイラルに陥ってしまう。
チームスタッフのみんなが「予算の作り方」を知らないと結果に反映されないことを知るべし。
疑問:地方のエンタメの可能性は?
地方のエンタメは可能性に満ちている。
特にオフライン。
テレビ祭りなんかが良い例として紹介されていました。
理由は、地方だと選択肢が絞られているから。
疑問:長期的に考える将来に勝つための戦略とは?
20代の集客は捨てろ
自分が40代としたら20代の話は聞かんだろうということ。
無理がある。
そこに広告費をかけても費用対効果は良くない。
だったら同世代に広告を打って、むしろそこの子ども世代を取りに行く。
子どもは10年先に財布を握る存在だから。
子どもの初めての経験を大事にする
「初めてだけは更新されない」
初めての記憶は覚えているもの。
だから初めての経験にはお金をかけてでも取りに行くべき。
もっと子どもの集客に力を入れて良い。
<例え:えんとつ町のハロウィンナイトの場合>
- 中学生以下は550円
- 未就学児は無料
そんな、子どもにとことんお得なプランを出す。
考えるべきは「お客さんの自宅の中にどうやって広告を打つか?」
- 毎日目につくのはかなりの広告になる。
- グッズも目的は広告であるということ。
- 子どもがファンになってくれると家庭内で強い広告になる。
- 子どもが毎日親にその話をする。親にねだる。機会が増える。
これは良いスパイラル。
西野さんの例、大きなアートパネルを売り出している。
引き出しにしまえないような巨大なもの。
だから飾るしかない。
すると毎日目に付く。
それが広告となる。
悩み:どこにファンをつければよいか?
Bリーグではホームだけが収益の機会。つまり年間30試合。
アウェーは持ち出しになってしまう。
そんな中で、選手にファンを付けてしまうとあまりに変数すぎて波が大きい。
選手が退団したらファンも離れていってしまう。
だから人ではなく、ハコにお客さんをつけることが重要。
ファンをハコにつけるか、選手につけるか?
チーム全員が戦略を共通理解していることが必要
西野さんの例として、メイン広告にキャストを出さないで宣伝をする。
「人の魅力を出さないとなると、どうやって人を出さずに集客するか?」
とスタッフが考え始める。
スタッフが自分の経験を思い出し、案を出し始める。
「どうやってハコにファンをつけるか?」と。
具体策を挙げるとすると?
バスケで考えると、アリーナの天井をもっとつけるのでは?
- 下向いてると重力で頬が下がり笑顔になりにくい
- 単純に、上を向いていると笑顔になりやすい
笑っているとそれだけで楽しい空間となり、楽しい記憶が残る。
《いかに上を向かせるかを考えるか》を考えてみる。
上を向くことが好印象な例
<海外の教会>
- 上に絵があって、
- 上から音が流れてきて、
- みんな上を向いて祈っている。
そして外に出てきたときにはスッキリした笑顔の人が多い。
これは上を見ている時間が長いのも要因の一つではないか、と。
<盆踊り>
また、盆踊りにはみんなが集まる。
その理由の1つは上を見るからだと。
- 踊り場は中央の高いところだし、
- いたるところにちょうちんが上に並んでいる。
今はだいたいBリーグではコートにプロジェクトマッピングで映像を映すことが主流のよう。
もっと上を見るような工夫が効果的かもしれない。
集客の上で、人にファンを付ける方針にしてしまうと対策につながらない
まず、選手にファンをつけることは、予測できない、安定しない変数ってこと。
加えて、そういった問題が起こったときに、スタッフが言い訳として考えがち。
問題なのはむしろ2番目の方で、
選手の移籍や欠場により集客に影響した場合、すぐに「仕方ない」という考えに落ち着いてしまう。
ここでもう一度、角度を変えて「どう工夫して集客しようか?」という発想・アイデアにつながらない。
だからハコにファンをつけることをスタッフ全体の統一事項として、全体で方法を考えるべし。
新規客獲得について
一見さんが入りにくい雰囲気ができてしまう問題
ある程度規模が拡大したときに、コアファンが付きすぎて新規のファンが入って来にくい環境はどう対応したらよいか?
→盛り上がりは良いのでそのままにしたい。
が、出してるコンテンツに対して良くない意味での宗教観が出ている。
解決策として、
圧倒的なクオリティのオープニングで魅了するしかない。
クラウドファンディングで一緒に作り上げる
また、例えばとしてコアファンを活かしてクラウドファンディングでオープニングを一緒に作り上げていくなんてどうか。
もっとカジュアルにクラウドファンディングを使っていけるような流れになるとよいかもしれない。
例えば地域で何かトラブルや問題が起きた場合、地域を助けようとしてクラウドファンディングを立ち上げる。
すると次には自分達のチームで問題が起こったときにログインしやすい。
が、問題点もある。
最終的には似たり寄ったりになってしまい、予算かけたのに差別化できないという結果になるかもしれない。
オープニングセレモニーに地元カラーを強調して差別化を図る
広く公開した場合には、知名度につながる効果を期待できる。
しかし注意点もある。
地元の人にとっては地元カラーは差別化ではなく日常ってこと。
本来、予算をかけて出来上がったものが非日常という矛盾。
このバランスを取るのが難しい。
ターゲットにすべきお客さんは寄贈者
お客さんは2パターンある。
寄贈者か、利用者か。
例えば、ランドセル。
- ランドセルを使うのは子ども。
- しかし購入するのは両親や祖父母。
- つまり、ランドセルは寄贈者に売っているってこと。
今のBリーグは利用者だけに売っている状態。
とにかく寄贈者に売ることを考えるべし。
寄贈者というのは、地元のVIPや経営者さんのこと。
地元のVIPや経営者さんにしっかりと営業する(メリットを提示して)。
その反面、一般の方には安く販売する。
寄贈者が買うメリット
大事なのは、
- 一般の方に対して「地元のVIPのおかげ」ということを伝えていくこと。
- するとみんなVIPに感謝する。
- VIPたちは感謝されるなら自分も、となっていく。
- 販売者が、一般の方に「VIPに感謝してくれてありがとう」まで伝える。
これは良いスパイラルになる。
大事なことは、一般の方に向けて、地元のVIPのおかげという教育をすること。
(島田チェアマンは最後に、お客さんに教育というとおこがましいので認知していただくといったニュアンスに言い換えられていました)
時間を味方にする
- 時間があると同じ広告でも届く人が増える
- 時間を味方にすると付加価値がつく
- するとスポンサーやVIPが集まりやすくなる
「自分達はココに感謝している」というメッセージをお客さんに届ける狙いもある。
メインスポンサーに対しては事あるごとにお声がけする。
チーム全体でメインスポンサー、お金の流れを周知していなければならない。
内容まとめ
収益を上げるにはどこに売り込むかが重要。
自分の商品を多くの人に届けるには広告が必要。
(長期戦略:子どもをファンにする、時間を味方につける)
普段から目に付くような広告戦略を立てる。(グッズや子ども)
具体的な流れとしては、VIPに貢献してもらい、感謝をリターンとして与えられる流れをつくる。そのためにはお客さんに認知してもらう環境づくりや働きかけが必要。
必要なのは「仕組みづくり」と「組織の教育」「大衆の教育」である。
動画のまとめは以上です。
おわりに
実践するのは難しいですが、
これからの時代自分の商品を持つことが必須になりそうです。
そういった中で、マーケティング戦略を学ぶことは重要となりそうですね。
自分の商品の精度を高め、それを届けるために経営を学んで、届けるべきところに広告をつける。
覚えておきたいと思います(´ω`*)